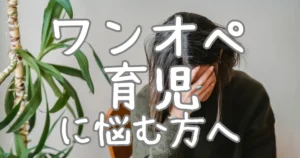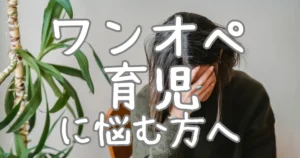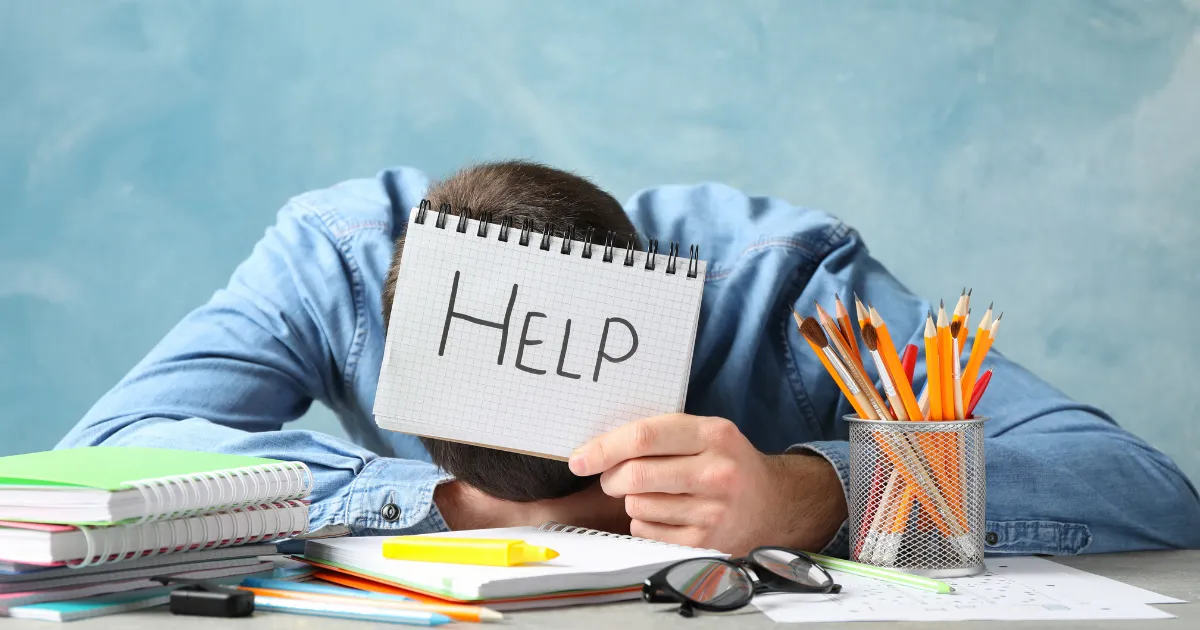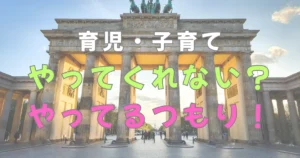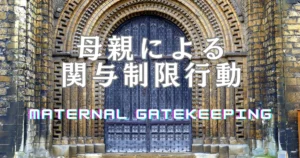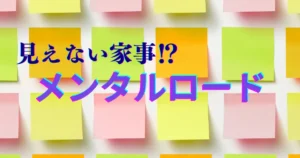日頃の育児で体がバキバキ…。
わかります。
私も慢性的な体のしんどさと、ずっと付き合ってきました。
育児をしていると、つい後回しにしてしまうのが、自分の体のケア。
「まだ大丈夫」「子どもが寝たらゆっくりしよう」——そんなふうに頑張り続けて、気づけば体は悲鳴を上げていた…という方も多いのではないでしょうか。
私自身も、子どもが赤ちゃんだった頃から今(3歳)に至るまで、首・肩・腰の痛みや寝不足からくる不調と日々付き合っています。
特につらかったのは…
- 長時間の抱っこで起きる手首や肘の違和感
- 睡眠不足による頭痛と倦怠感
- 寝相の悪さで生じる腰や肩の痛み
育児って、本当に体力勝負ですよね。
でも、そんな中でも「少し楽になる工夫」を取り入れることで、なんとか日々を乗り越える力が生まれてきました。
- 育児中に起こりやすい体の不調と原因
- 少しでもラクになるためのケア・対策方法
- 忙しい毎日でもできるセルフケアの工夫
- 無理しないマインドの持ち方と、人との関わり方
「完璧じゃなくていい」
そんな気持ちで読んでもらえたら嬉しいです。
育児中に起きやすい体の不調と原因


症状はひとつではありませんでした。
以下は、私が実際に感じた不調とその原因です:
| 不調 | 原因 |
|---|---|
| 頭痛・倦怠感 | 睡眠不足、慢性的な疲れ |
| 首・肩の痛み | 抱っこの継続、ミルクの姿勢、子どもの寝相(頭突き・しがみつき) |
| 腰痛 | 長時間の抱っこ、無理な姿勢での授乳 |
| 手首・肘の痛み | 抱っこや寝かしつけ時の体勢、同じ動作の繰り返し |
どれも、日々の積み重ねで生まれる疲れが引き起こしていました。
少しでもラクになるために。私が試してよかったこと


全部が劇的に効いたわけではありません。
でも、「ちょっと楽になったかも」と思える瞬間があるだけで、心がずいぶん軽くなります。
1. ストレッチ・軽い筋トレ
痛む部位の周りをやさしく動かす。
腰痛は、背筋をゆるく鍛えると安定感が出て、痛くなる頻度が減りました。
無理に頑張るより、「少し動かす」くらいの意識で大丈夫です。
2. 整体・マッサージ
「もう限界」と思ったときはプロの手を借りることで、心まで整ってリフレッシュできました。
3. 熱めのお風呂に入る
筋肉がじんわりほぐれて、よく眠れるようになります。
温泉のもとなどを入れると、体も気持ちも少しラクに。
4. 抱っこを減らす工夫
成長に合わせて、ベビーカー・おんぶ・歩く練習などに切り替え。
無理して抱っこを続けず、方法を変えるだけでも負担が減りました。
5. 子どもの寝相対策
寝る位置の調整(右側→左側など)で肩や腰の負担が変わりました。
子どもが気に入る枕を導入(うちは電車のタオルがヒット)。頭の位置が正しい位置に来るとしばらくは頭突きや蹴りが来ません。
6. 湿布・鎮痛剤をうまく使う
ロキソニンの湿布などで一時的に痛みをやわらげる。
頑張りすぎず、「今日は頼ろう」と思える日も大切に。
7. 「休む日」を意識して作る
協力してくれる人がいるときは、意識的に休むと決める。
睡眠の質が変わるだけで、翌日の体が全然違いました。
8. 香りや飲み物でリラックス
好きなアロマ、あたたかい飲み物などでリセット。
「五感から癒す」って、思った以上に効果があります。
9. 栄養ドリンクもたまにはアリ
気休めと思っていたけど、意外と効いた日もありました。
慢性的な疲れのときには助けられます。
人によって“つらさ”の感じ方は違う
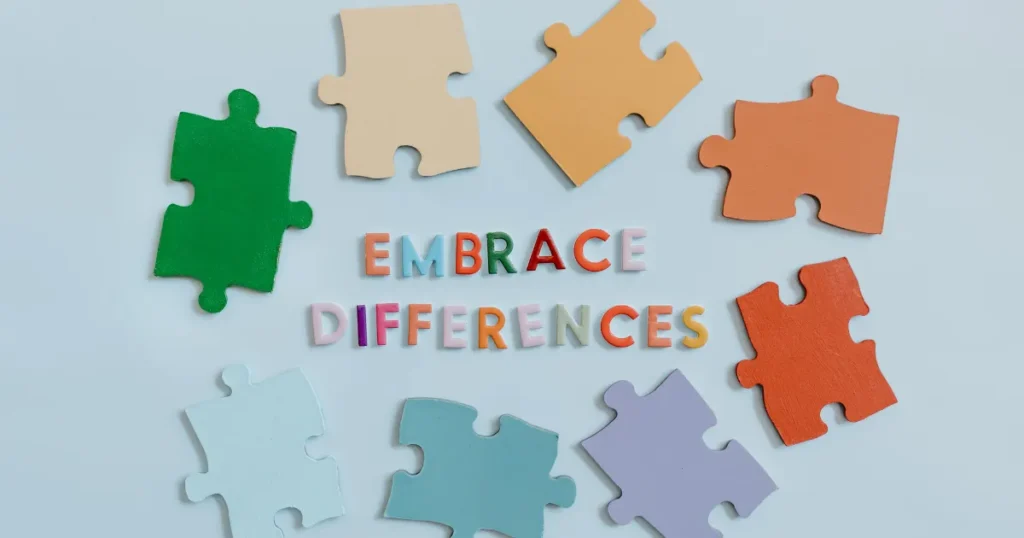
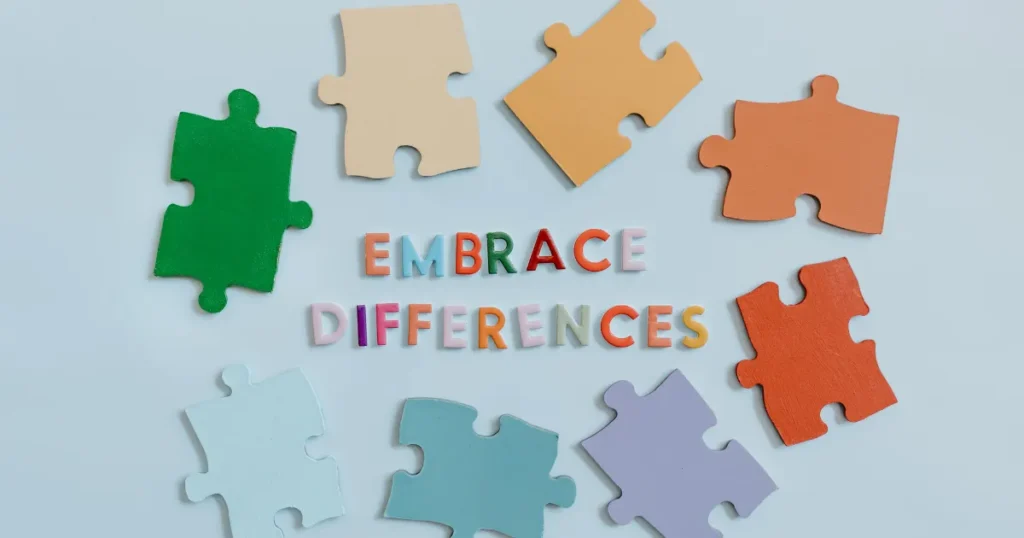
育児のしんどさは、人によって感じる場所も重さも違います。
「どうして自分だけこんなにしんどいの?」と思うこともありますよね。
でもそれは、体のつくりや筋力、育児環境の違いがあるから。
だからこそ、自分がつらいときは「つらい」と言って、周りに知ってもらいましょう。
そして、他の人のつらさも否定しないで、受け止めてあげてください。
感じ方の違いを受け入れることが、育児の人間関係をラクにしてくれます。
まとめ
育児中の体の不調は、一気に解決できるものではありません。
でも、「今日は少しラクだったかも」「昨日よりちょっとマシだった」そう感じられるだけで、前向きになれることもあります。
完璧じゃなくていい。「今日はここまで」と区切っていいんです。
疲れた自分に、「今日もおつかれさま」と声をかけてあげてください。
体をいたわることも、大事な育児のひとつです。
無理せず、自分のペースで少しずつ。
心と体をアップデートしながら、ラクな育児を続けていきましょう。