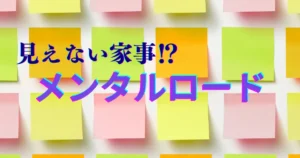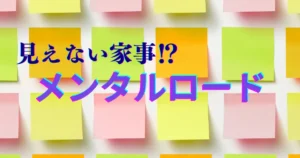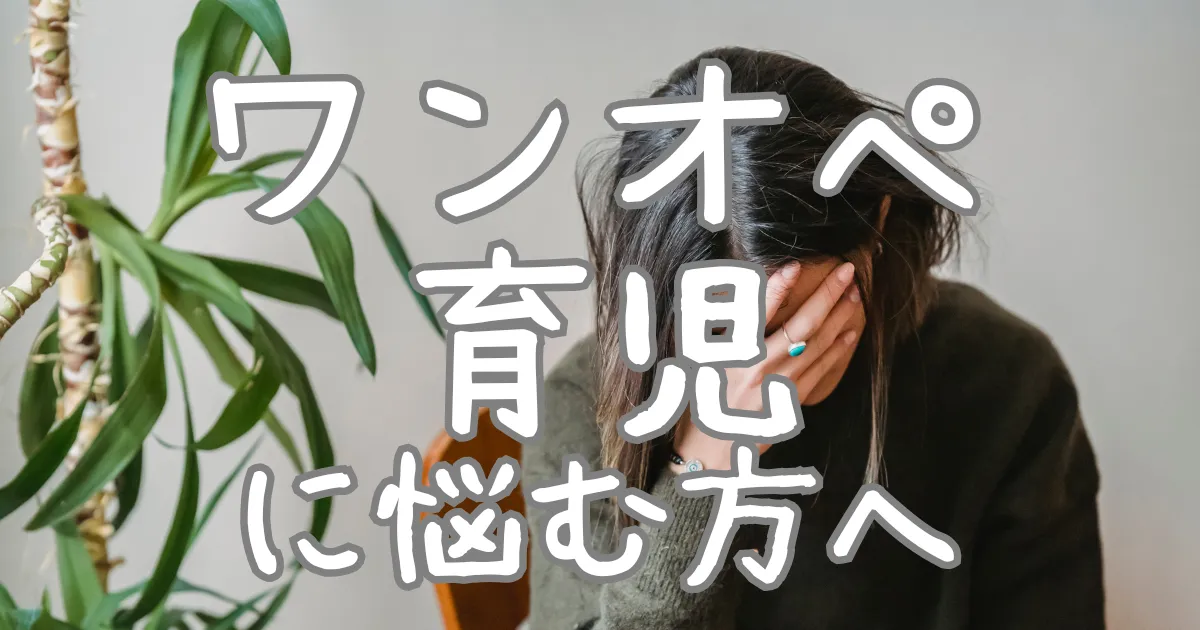「朝から晩まで、子どものことばかり。自分の時間が全くない…」
そんな感覚に、心当たりはありませんか?
このページをご覧になっているということは、
今、育児や家事を“ひとりで抱えている”ことに限界を感じているのではないでしょうか。
- 朝から晩まで子どもと向き合い、一人になれる時間がまったくない。
- 何をするにも“中断”されて、気が休まる瞬間がない。
- 夜中に何度も起こされて、いつ熟睡できたかわからない。
それでも「親だから頑張らなきゃ」と気を張り続け、疲れても、泣きたくても、頼れる場所がないと感じていたら——
あなたは今、まさにワンオペ育児の渦中で、心も体も疲れきっている状態かもしれません。
- ワンオペ育児とはどんな状態か
- その影響と原因
- 乗り越えるためのヒント
ワンオペ育児とは?


ワンオペは、ワンオペレーション(One Operation)の略。
もともとは飲食業などで「1人で業務を切り盛りすること」を指す言葉です。
今では「家庭内での家事・育児を実質的に一人で担っている状態」を表す言葉として、ワンオペ育児が用いられています。
以下のような状況に心当たりがある場合、ワンオペ育児と言えるかもしれません。
- パートナーが単身赴任、または仕事で長時間不在
- 夫婦どちらかが子育てに非協力的、もしくは協力できない
- 実家が遠方にあり、支援が得られない
- シングルマザー/シングルファザーで育児・家事・仕事すべてをこなしている
性別に関係なく、育児のほぼすべてを一人で担っている状態が続くと、心も体も疲弊していきます。
ワンオペ育児が引き起こす3つの影響
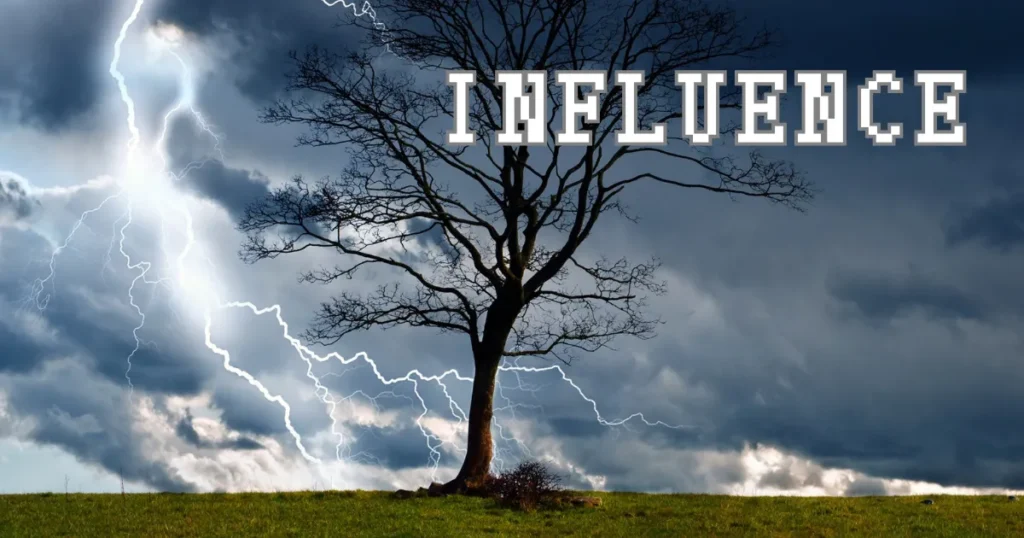
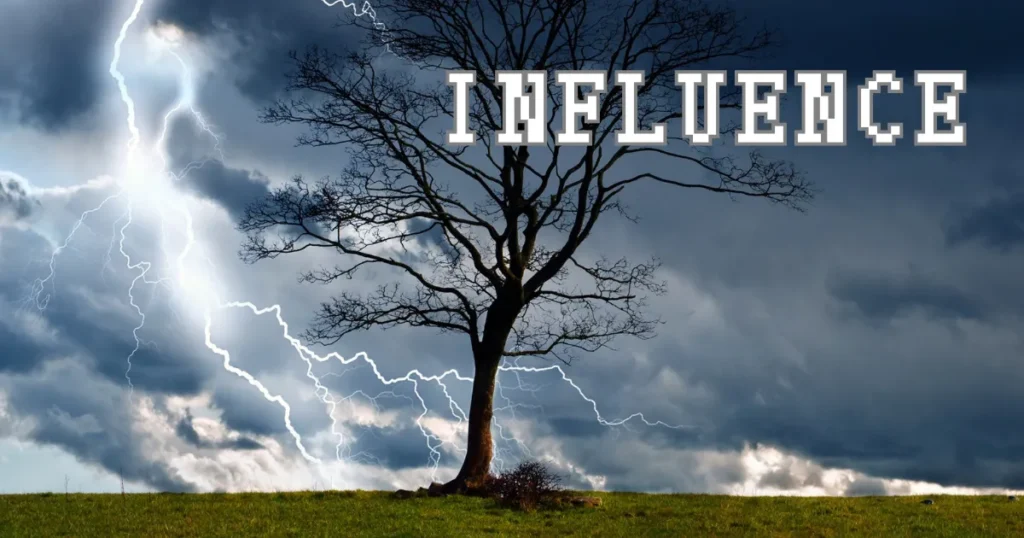
「誰にも頼れない」「ひとりで抱え込んでいる」育児は、想像以上に大きな負荷を心と体に与えています。
ワンオペ育児が長期化すると、疲労やストレスをはじめ、家族や社会との関係にまで、影響を及ぼしてしまうのです。
ここでは、ワンオペ育児が引き起こす「3つの負担」について、見ていきたいと思います。
- ① 心と体への影響
(慢性的なストレスと自己否定感) -
- 常に気を張った状態が続くため、緊張や疲労が少しずつ蓄積していきます。
- 思うように感情をコントロールできず、「怒りたくないのに怒ってしまう」場面が増え、自己否定につながることもあります。
- 外との関わりが減ることで、孤独感や社会から取り残されたような気持ちになることも少なくありません。
- ② 家庭内のひずみ
(パートナー関係や家族の空気に影響) -
- 負担が偏る状況が続くと、「どうして自分ばかり」と感じるようになり、パートナーへの不満が心の中に積もっていきます。
- そのストレスが子どもに向かってしまうと、あとで強い自己嫌悪を感じることにもなりかねません。
- こうした緊張感が家庭全体に広がると、家族が安らげるはずの空間が、いつしか息苦しさを感じる場所になってしまいます。
- ③ 社会からの孤立感
(母親らしさ・父親らしさに縛られる) -
- 女性の場合、「育児は母親が中心でやるもの」といった昔ながらの考えが、今も根強く残っています。
そのため、育児中の親が外に頼ることをためらったり、支援を受けづらかったりする状況が生まれがちです。 - 男性の場合、「仕事を優先すべき」「男性がメインで育児をするのはおかしい」といった価値観が、職場や社会の中で今なお根強く残っています。
そのため、仕事と育児の両立や、地域の活動に参加することが難しい状況があります。 - 結果として、家の中にこもりがちになり、社会とのつながりがどんどん薄れていき、社会から取り残されているような感覚に陥ってしまうこともあります。
- 女性の場合、「育児は母親が中心でやるもの」といった昔ながらの考えが、今も根強く残っています。
なぜワンオペになるのか?
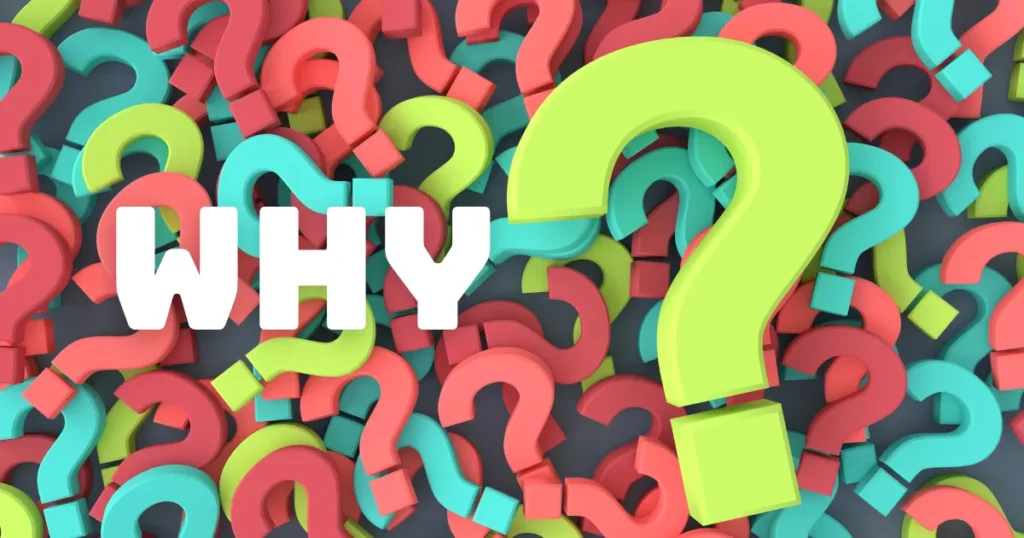
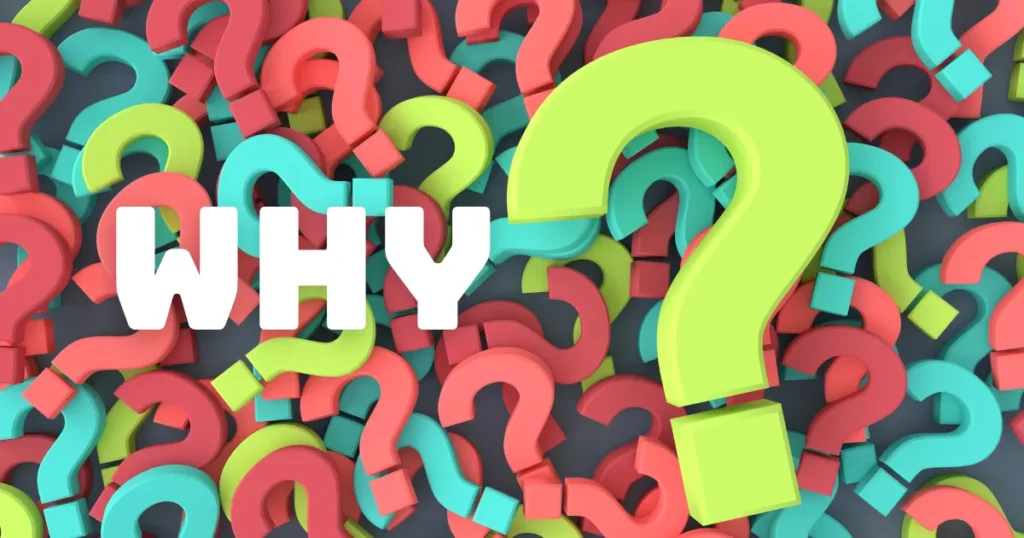
日本の育児において、なぜこんなにも偏りが生まれてしまうのでしょうか。
「仕方ない」と済まされてきた背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。
ここからは、ワンオペ育児を引き起こす主な要因について、見ていきましょう。
ワンオペを引き起こす5つの要因
- ① パートナーが物理的に関われない状況
(単身赴任、夜勤など) -
- 仕事の都合で家庭にいる時間が圧倒的に少ない場合、育児や家事を任せたくても物理的に難しいという現実があります。
- 単身赴任や夜勤・長時間労働など、働き方によっては平日はもちろん、休日すら家族との時間を確保できないケースも珍しくありません。
- ② 価値観のズレや、育児への温度差
(やってるつもり問題) -
- 「やっている」と感じているパートナーと、「全然足りていない」と感じている側との間にギャップがあると、負担は一方に偏りやすくなります。
- たとえば、週末に子どもと少し遊んだだけで「育児に参加している」と認識されてしまうと、日々の細かな対応を担う側は不満を抱えがちです。
- ③ 核家族化・地域サポートの希薄さ
(実家が頼れない) -
- 近くに頼れる家族や親戚がいない、または高齢・就労中などの理由でサポートを受けられないという状況も多くあります。
- 特に核家族化が進んだ現代では、育児を家庭内だけで完結させようとすると、どうしても主担当者に負担が集中しやすくなります。
- ④ 家事・育児タスクの可視化不足
(気づいた方がやる問題) -
- 「必要なことを必要なときに気づいて動く」という見えない労力は、想像以上に大きなものです。
しかし、多くの家庭では、家事・育児のタスクがリスト化されておらず、分担が曖昧なまま。 - 「気づいた方がやる」状況が続くことで、無意識のうちに一人が背負い込んでしまうこともあります。
- 「必要なことを必要なときに気づいて動く」という見えない労力は、想像以上に大きなものです。
- ⑤ 自分を追い込みがちな性格
(頼っちゃいけない・甘えちゃいけない) -
- 「自分が頑張らなきゃ」「これくらいで弱音を吐いてはいけない」と自分を追い込んでしまう。
- 責任感が強い人ほど、「頼る」ことに罪悪感を抱いてしまい、限界が来るまで一人で背負い続けてしまう傾向があります。
対処法


負担の偏りや疲弊感を、「仕方ない」と受け入れ続けてしまうと、心も体も限界を迎えてしまいます。
大切なのは、“全部自分でやる”前提を、少しずつ手放していくことです。
無理を続けるのではなく、「どうすれば今よりラクになれるか」を考えること。
それは甘えではなく、育児を続けるための前向きな工夫です。
①「完璧じゃなくていい」と自分を許す
育児も家事も、理想どおりに進まないのが当たり前です。
「ちゃんとやらなきゃ」「周りはもっとできているのに」——
そんな思いに縛られていると、心も体もすり減ってしまいます。
ときには手を抜いたり、優先順位を下げたりすることも、子どもにやさしく向き合い続けるために必要な“調整”です。
がんばり屋さんほど、気をゆるめることに意識を向けてほしいです。
② 支援サービスを迷わず活用
どれだけ意識しても「時間が足りない」「ひとりでは限界…」という状況があります。
そんなときこそ、大切なのが外部の力を借りることです。
家事や育児を全部自分で抱え込まずに、頼れるサービスを味方にすることで、心にも時間にも余白が生まれます。
今は、家庭のかたちやライフスタイルに合わせて選べるサポートも増えています。
| 支援の種類 | 例 | 効果 |
|---|---|---|
| 家事代行 | CaSy・タスカジ | 時間と心のゆとりを確保 |
| 冷凍弁当 | mogumo・nosh | 食事準備の負担を軽減 |
| 一時保育 | ファミサポ・自治体支援 | 自分だけの時間を確保 |
| ベビーシッター | キズナシッター等 | 緊急時・夜間も対応可 |
育児=孤独ではなく、育児=チームでやるものに発想を切り替えることが大切です。
③ パートナーと“分担”を再確認
家事や育児のタスクを一つひとつ書き出してみると、「どちらが・どれだけ」担っているかが、初めて見えてくることがあります。
特に、“やってない”のではなく、“見えていない”だけというケースは少なくありません。
そのうえで、「こうしてほしい」ではなく、「自分はこう感じている」といった言い方で気持ちを伝えることが大切です。
相手を責めるのではなく、事実と気持ちを丁寧に共有する姿勢が、負担の見直しや役割の再設計への第一歩になります。
④ 自分だけの時間を持つ
忙しくても、1日の中に“自分を取り戻す瞬間”をほんの少し持つことは、心のバランスを保つうえでとても大切です。
たとえ5分でも、誰にも邪魔されない時間があると、気持ちに余裕が生まれます。
| 行動 | 効果 |
|---|---|
| 好きな音楽を聴く | 思考の切り替えや情動調整に役立ち、ストレス緩和につながる |
| 温かい飲み物を飲む | 副交感神経の働きを高め、自律神経のバランスを整える |
| 好きな動画を1本見る | 笑いや感動によるカタルシス効果で、心理的ストレスを解放する |
| 深呼吸をする | 迷走神経を刺激し、副交感神経優位(リラックス)の状態へ導く |
まとめ
「どうして自分ばかり……」
そう感じたとき、責めるべきはあなた自身ではなく、“育児の偏り”です。
気づかないうちに、育児も家事も心の余裕さえも、すべて自分で抱え込んでしまっていた。
そんな毎日は、本当につらくて当然です。
でも、忘れないでください。
育児はひとりで完璧にこなすものではなく、支え合いながら少しずつアップデートしていくものです。
たとえば──
- 家事代行や冷凍弁当などの外部サービスに頼る
- パートナーと家事・育児の再分担について話し合う
- 「自分の時間」を意識的に確保する
これらはすべて、「ラクをすること」ではなく、
子どもにやさしく向き合い続けるための前向きな選択です。
育児のかたちは、家庭によって違っていて当然。
「こうあるべき」にとらわれず、自分たちに合った形に柔軟にアップデートしていくことが、家族全員の心の健康を守る鍵になります。
育児を“ひとりの仕事”にしない。
それが、家族にも、自分自身にも、そして社会にもやさしい育児の第一歩です。