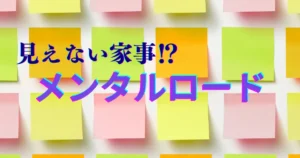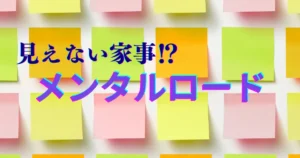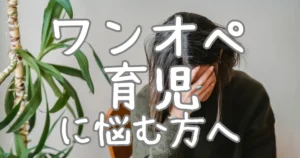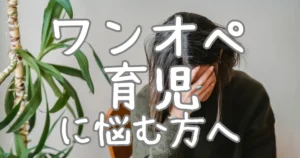「やっても文句を言われるから、最初からやらないほうがいいかも…」
「自分が関わることで、妻の負担になっている気がする…」
育児に関わろうとしたものの、うまくいかなかった経験から、いつの間にか「自分はやらない方がいい」と引いてしまっていませんか?
それはもしかすると、パターナルゲートキーピング(paternal gatekeeping)という心理が関係しているかもしれません。
- 育児に関わりたいけれど、うまく馴染めない
- 手を出すと文句を言われる気がして、引いてしまう
- 「自分は苦手だから」と無意識に距離を置いている
もし、少しでも心当たりがあるなら――
この記事を読むことで、その違和感や“引いてしまう理由”が見えてくるかもしれません。
- パターナルゲートキーピングとは何か?
- なぜ父親が“育児から距離を取る”構造が生まれるのか
- 家族と関わるための視点の持ち方・行動のヒント
パターナルゲートキーピングとは?


パターナルゲートキーピング(paternal gatekeeping)を直訳すると、
父親による門番行動
単語ごとの意味は、
パターナル(paternal)
:父親の、父性的な
ゲートキーピング(gatekeeping)
:出入りを管理すること、制限・選別をすること(門番的役割)
育児の分野では――
父親が無意識に「育児は自分の役割ではない」と距離を取り、関わることを自ら制限してしまう心理や行動を指します。
パターナルゲートキーピングでは、以下のような思考や行動が見受けられます。
心理的背景(無意識の思考)
| 心理 | 内容 |
|---|---|
| 否定される不安 | 「やってもどうせダメ出しされる」「間違えたら責められる」 |
| 経験の不足・自信のなさ | 「自分には育児は向いてない」「どう接していいか分からない」 |
| 役割の固定観念 | 「育児は母親の仕事」「自分は稼ぐほうが貢献できる」 |
| 相手のペースに遠慮 | 「手を出すとリズムが崩れそう」「妻のほうが慣れてるし…」 |
典型的な行動例
| 行動 | 説明 |
|---|---|
| 任せっぱなしになる | 子どもの対応をすべてパートナーに依存し、自ら関わろうとしない。 |
| 頼まれたときだけ動く | 自主的には動かず、「やって」と言われてから動く。 |
| 関与しないことを正当化する | 「自分より相手のほうがうまくやれる」 「口出ししないほうが平和」などと距離を置く理由を探す。 |
| 失敗を恐れて消極的になる | 過去のミスや否定を引きずり、「もうやらないほうがいい」と思い込む。 |
こうした思いが積み重なると、育児は“相手に任せるもの”という姿勢が定着しやすくなります。
似たような言葉に “マターナルゲートキーピング” というものがあります。
どちらも門番という点では共通していますが、行動面では逆の意味で使われます。
マターナルは「コントロールと囲い込み」のニュアンスが強く、
パターナルは「自ら距離をとる・降りる」というニュアンスが強い。
つまり、ゲートを“閉める”理由が違うのです。
パートナーの行動や心理を理解する手助けにもなるので、ぜひチェックしてみてください。
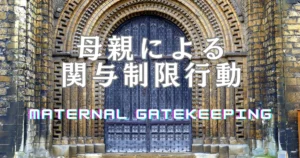
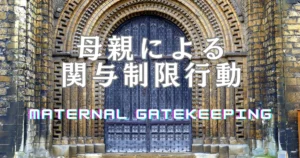
なぜ起こるのか?
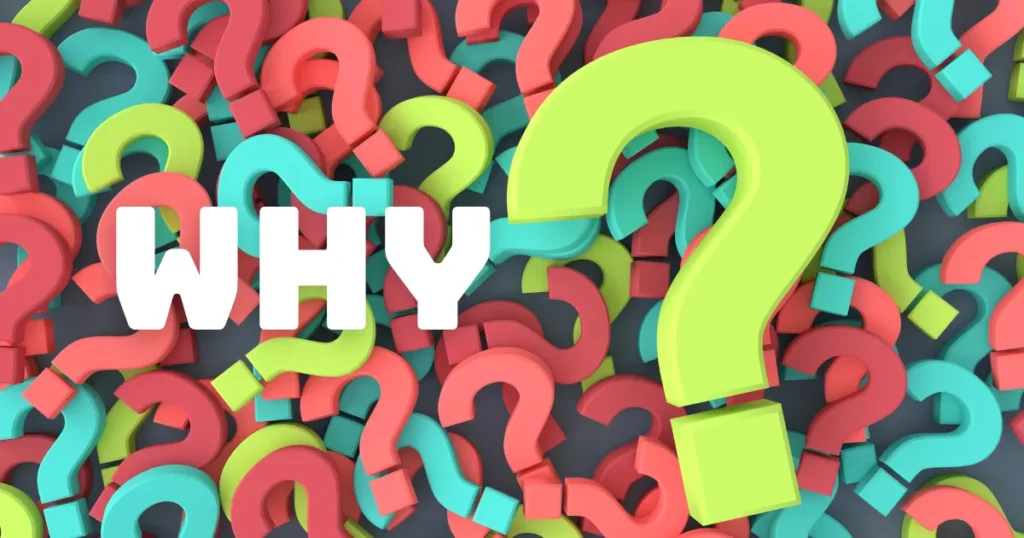
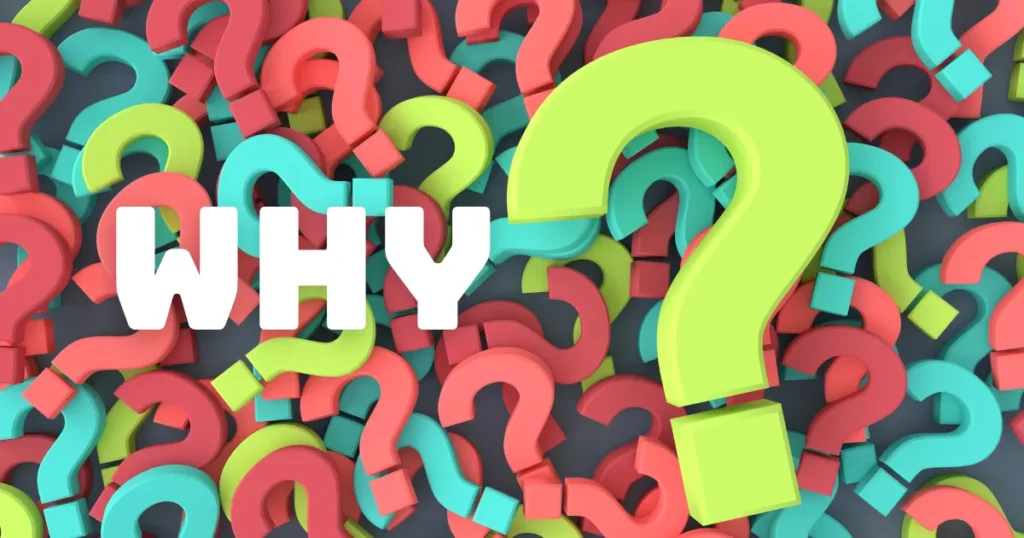
パターナルゲートキーピングは、ただ「やる気がない」「無関心」といった単純な理由では説明できません。
その背景には否定される不安や自信のなさ、役割意識のすれ違いといった、さまざまな心理的要因が複雑に絡んでいます。
さらに、母親側のマターナルゲートキーピングと相互に影響し合いながら形成されるケースも多く見られます。
ここでは、パターナルゲートキーピングがなぜ起こるのか、その主な原因を整理してみましょう。
- 自信のなさ・比較意識
-
- パートナーが育児をスムーズにこなしている姿を見て、「自分の出る幕じゃない」と感じてしまう。
- 育児に慣れていない段階での、ちょっとした指摘や失敗が自己肯定感を大きく揺さぶる要因になり、「やるたびにダメ出しされるくらいなら、最初から関わらない方がいい」と、距離を取る選択をしてしまう。
- 「自信がない → 比較して引いてしまう → 経験値が増えない」というループが生まれている。
- 経験機会の少なさ
-
- 出産・育休期間を経て、育児の主導権がパートナーに偏り、「どこに何があるかも分からない」「一から説明してもらわないと分からない」状態。
- 「自分には入っていけない世界」という心理的ハードルから、「任されない → 経験がない → さらに関与しづらくなる」という悪循環が固定化。
- 「役割の外側にいる」という感覚が強まり、ゲートの外に留まる。
- ジェンダー規範・思い込み
-
- 「母親の方が子どもにとって安心/男は育児が苦手なもの/育児より稼ぐ方が貢献できる」
というジェンダー規範や社会的刷り込みにより、「育児は自分の役割ではない」と思い込む。 - ジェンダー規範を持った周囲の言動(祖父母や同僚、友人など)によって、積極的に関わろうとする気持ちが抑制される。
- 「母親の方が子どもにとって安心/男は育児が苦手なもの/育児より稼ぐ方が貢献できる」
こうした違和感や孤立感が、結果としてゲートの前で立ち止まり続ける心理を強める要因となります。
引き起こされる影響
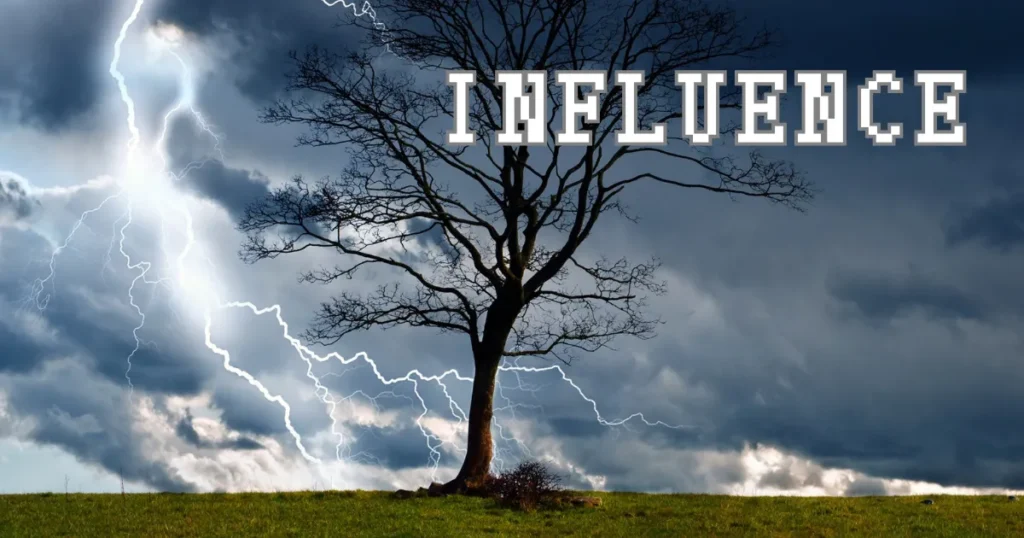
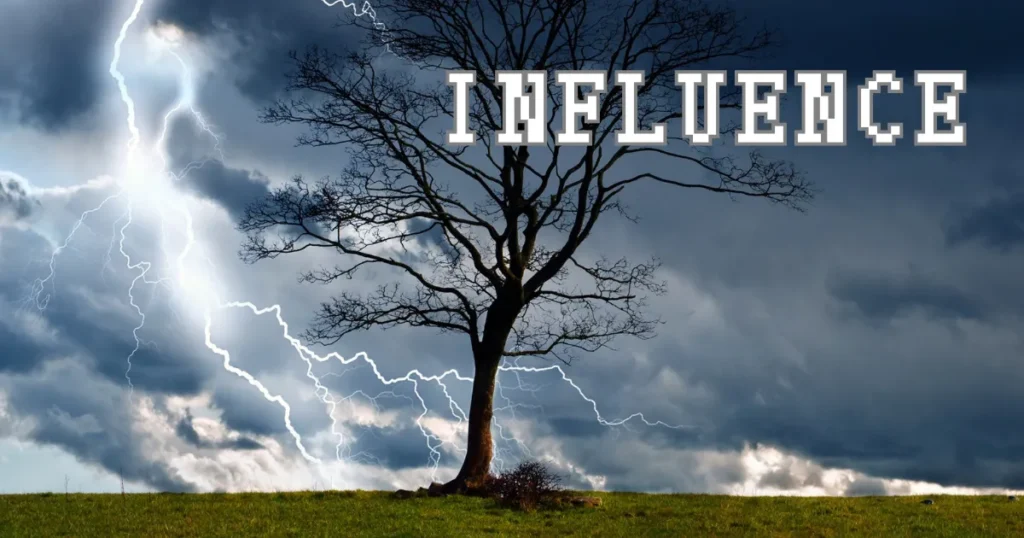
こうした心理や構造が重なることで、単なる“関わりの制限”にとどまらず、家族全体の関係性や育児の質にも、少しずつ影を落としていきます。
「やらない」「任せられない」状態が続くと、当事者だけでなく、パートナーや子どもにも悪影響が現れてくるのです。
では、実際にどのような影響が生まれるのでしょうか?
- 自分自身への影響
-
- 子どもとの信頼関係を築く機会が減る
日常の関わりが少ないことで、子どもと自然な関係性を築くタイミングを逃しやすくなります。 - 育児に関与できないことへの劣等感や孤立感
「自分は育児に役立っていないのでは…」という思いが募り、家庭内での存在意義を見失いかねません。 - 「家のことがわからない」ことで将来的に不安が増す
進学や病気など将来の場面で、子どもに関する判断ができない・情報が乏しいことが不安の種となります。
- 子どもとの信頼関係を築く機会が減る
- パートナー・家庭への影響
-
- 片方だけが疲弊する構図が強化される
一方がケアや管理の大半を担うことで、心身の負担が偏り、慢性的な疲労や不満が蓄積します。 - 「結局わかってくれない」という感情的な断絶が生まれやすい
育児に関する苦労や判断を共有できないことが、パートナー間の信頼や対話の機会を奪っていきます。 - 子どもにとっても偏った接触パターンが定着するリスク
“お世話は母親、遊びは父親”のように役割が固定されすぎると、多様な関係性の学びを妨げてしまう可能性もあります。
- 片方だけが疲弊する構図が強化される
育児に関わるためのヒント


「どうせ自分はうまくできない」「口を出すと嫌がられそう」——
そんな風に思って、一歩引いてしまうことがあるかもしれません。
でも、育児は“完璧にこなす”ことより、“関わり続ける”ことが何より大切です。
最初から上手くやろうとせず、小さなステップを積み重ねていけば、少しずつ自信が生まれ、家庭内での信頼関係も深まっていきます。
ここでは、無理なく育児に関わっていくための具体的なヒントをご紹介します。
① “できない”から始めていい
育児は、やってみて初めて分かることの連続です。
最初から器用にできる必要はありません。
「どうしたら泣き止むのか」「何が好きなのか」など、わからないままでも、一緒に過ごすことで自然と見えてくるものがあります。
“うまくやる”ではなく、“まずはやってみる”という姿勢が大切です。
② パートナーのやり方と「違ってもいい」
子育てにおいては、「同じようにやること」=ベストではありません。
「ママはこうしてたのに」「やり方が違う」と言われると不安になるかもしれませんが、
“自分らしいやり方”で関わることが重要です。
たとえば、読み聞かせの声のトーンや遊び方など、父母の関わりが異なることで、子どもにとっては多様な刺激や学びにつながります。
③ 小さな“関与”を積み重ねる
いきなりすべてを担おうとせず、自分が関われる場面を見つけることがポイントです。
たとえば…
- 朝の送りだけを担当する
- 毎晩、絵本を読む役割を担う
- 週末は子どもと出かける時間をつくる
こうした“関わる場面”を持つことが、家庭内の信頼や自信につながります。
④ 完璧でなくていい
育児は、「うまくやる」ことが目的ではありません。
大切なのは、そばにいること・向き合おうとすることです。
失敗しても、やり方がぎこちなくても、
一緒に笑って、一緒に困って、一緒に悩むことが、子どもにとっての安心になります。
放っておくと、関係は知らず知らずのうちに悪くなります。
でも、たったひとつの行動が、家庭の空気をやわらかく変えるきっかけになります。
まとめ
パターナルゲートキーピングは、
「否定されるくらいなら、関わらないほうがいい」という“防衛的な選択”の積み重ねから生まれます。
でもその裏側には、「関わりたいのに、うまくいかなかった」という経験や、「失敗したくない」という不安があるはずです。
だからこそ、
- 完璧じゃなくても一歩踏み出し、関わってみる。
- 勇気を出して、自分から声をかけてみる。
その小さな行動が、
孤立しがちな育児を “一緒に進む育児”へとアップデートしていく鍵になります。
たとえば、今日の夜は絵本を1冊選んで一緒に読んでみる。
そんな一歩から、関係は少しずつ変わっていきます。