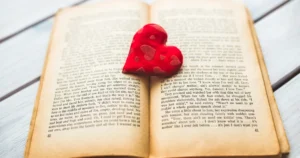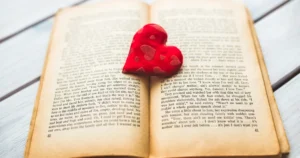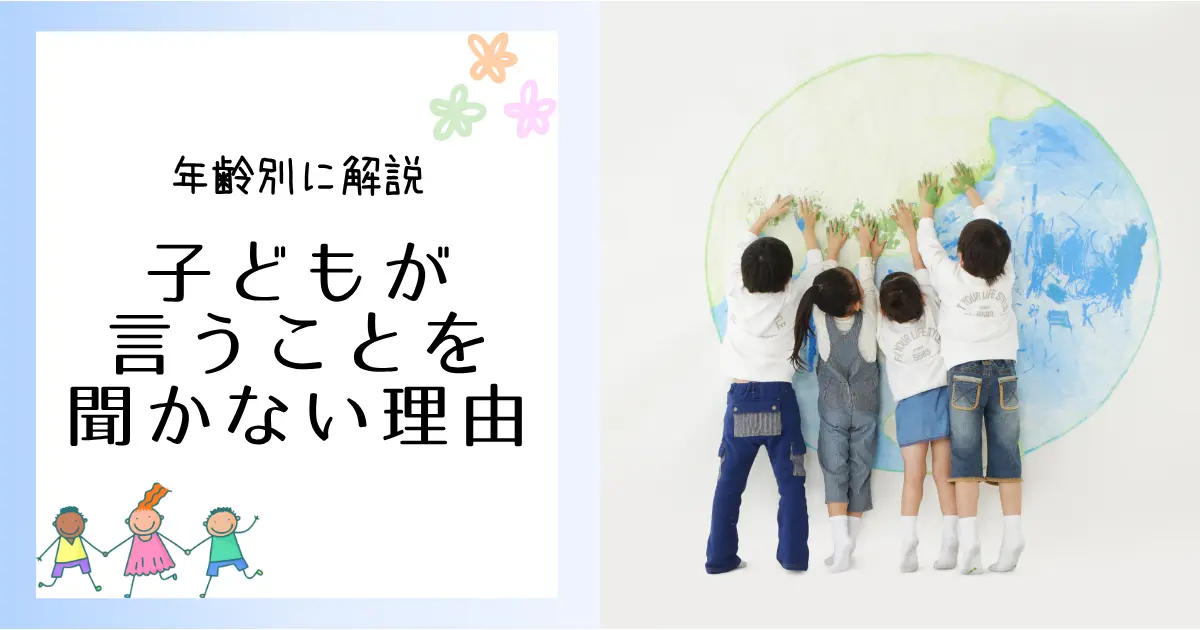何度も同じことを注意をしたくない
ダメなことを繰り返されてつらい
実は、子どもには“聞けない理由”があるんです。
- 何度も注意してるのに、まったく同じことを繰り返される
- 名前を呼んでも無視されているように感じる
- 「わざとやってるの?」と思うような反発やふざけた態度
- 頼んだ行動をしないまま、遊び続けている
- 「今やろうとしてたのに!」と逆ギレされてモヤモヤ…
そんな毎日に、思わずイライラしたり、落ち込んだりしてしまうこと、ありませんか?
実は、言うことを聞かないには理由があります。
子どもの“聞かない”という行動の裏には、発達段階に応じた「まだ聞けない」理由が隠れていることがとても多いのです。
親がちゃんと伝えたつもりでも、子どもにはまだ届かない・まだ切り替えられない・まだ納得できない
…そんな背景があるかもしれません。
だからこそ、伝え方や関わり方を少し見直すだけで、子どもの反応が驚くほど変わることもあります。
- 年齢ごとに違う「聞けない」理由とその背景
- 声かけや関わり方を少し変えるだけで伝わる、実践的なヒント
- 親子の衝突を減らし、“できた!”が増える関わり方の工夫
- 子どもの心を傷つけず、自己肯定感を育む声かけのコツ
「言うことを聞かない子」ではなく、「まだ聞けない子」なんだと捉える視点を持つことで、親子の関係はぐっとラクになります。
本記事が、そんな視点のアップデートのきっかけになりますように。


年齢別でわかる「まだ聞けない」背景と対応
子どもが親の声かけに反応しないとき、「聞こえてないの?」「わざと?」と感じてしまうことがありますよね。
しかし実際には、“反抗している”のではなく、“まだできない”段階にあることが多いのです。
子どもの発達はおよそ1〜2年ごとに質的に変化するとされており、それに応じた対応が必要です。
【1〜1.5歳】“伝わらない”のがあたりまえの時期
- 特徴
-
1歳を過ぎると、表情が豊かになり、言葉も少しずつ出てきます。
けれど、まだ言葉の意味をしっかり理解して行動に移すことはできません。
この時期は、親の声かけが“意味”として届いていない前提で関わることが大切です。
- よくある困りごと
-
- 名前を呼んでも振り向かない
- 危ないものに何度も手を伸ばす
- 「ダメ!」と言うと、余計に泣いたり怒ったりする
「聞こえてるのに無視してる?」と思うかもしれませんが、
集中しているときは周りの音が入ってこないのが普通です。 - 背景にある“脳の仕組み”
-
- 注意を向けられる時間は数秒程度と、とても短い
- 親の声は、まだ“意味のある言葉”ではなく“音のかたまり”として処理されている
- 「自分がやりたいこと」が最優先で、止まる・切り替えるといった制御はまだ難しい
つまり、「言ったのにできない」のではなく、“まだ理解できない・制御できない”状態なのです。
- 親にできる工夫
-
- 言葉だけで伝えようとせず、手ぶりや表情、視線の方向で伝える
- 危ないときは、言葉で止めるより、手をそっと止めて安全な方向に誘導する
- 伝わらないのが普通だと思って、「まだわからないよね」と心に余裕を持つことがいちばんの対策です
例:
「熱いからダメ!」と大きな声で制止するより
→ 静かに手を止めて「こっちはさわっても大丈夫だよ」とやさしく示す。
【1.5〜3歳】“イヤイヤ期”は「自分で決めたい」のサイン
- 特徴
-
「イヤ!」「じぶんで!」という言葉が急に増えて、戸惑った経験はありませんか?
この時期の子どもは、自我が大きく育ちはじめ、親に言われたからやるよりも、
自分で決めたい気持ちが強くなっていきます。大人にとっては“わがまま”や“反抗”に見える行動も、心の成長のあらわれです。
- よくある困りごと
-
- 着替えや歯磨きを全力で拒否する
- 外出準備になると、わざとふざける
- 「ダメ」と言うと泣き叫んだり、ひっくり返る
「何度言っても聞かない」「毎日同じやり取りでヘトヘト…」という声もよく聞きます。
でも実は、それも“親に支配されたくない”という自然な成長過程なのです。
- 背景にある“こころの動き”
-
- 脳の前頭前野はまだ未熟で、感情のコントロールが難しい
- 言われたからやるではなく、自分で決めたという実感が必要
- 自分の気持ちをうまく言葉にできないことで、爆発的な癇癪につながることも
この年齢では、行動でしか気持ちを表現できないことが多いのです。
- 親にできる工夫
-
- 選択肢を提示して主導権を渡す:「靴は赤と青どっちがいい?」
- 「○○したかったんだね」と、まず気持ちに共感する
- 癇癪には無理に動かそうとせず、“落ち着くのを待つ”ことが大事
例:
「まだ遊びたいよね。でもそろそろお風呂の時間だよ。」
「アヒルさんも連れて行って一緒に入ろうか?」「自分で選んだ」と感じられれば、子どもは驚くほどスムーズに行動することがあります。
【3〜5歳】理解はしている。でも「気持ち」が切り替わらない
- 特徴
-
3歳を過ぎると、話の内容をしっかり理解してくれる場面が増えてきます。
「これ終わったらごはんだよ」「片づけたら遊びに行けるよ」といった言葉も通じるようになり、
ついわかってるんだからできるはずと期待してしまいがちです。でも実際には、気持ちが切り替わらずに行動に移せないことがたくさんあります。
- よくある困りごと
-
- 「もう1回!」を繰り返して、遊びが終われない
- 声をかけてもおもちゃを片づけようとしない
- 注意すると「うるさい!」「やろうとしてたのに!」と逆ギレ、あるいは黙り込んで拗ねる
「言ってることは理解してるのに…」と思う瞬間、ありますよね。
でもこの年齢は、“感情”が“理解”より先に動くのが自然な段階なのです。
- 背景にある“こころの動き”
-
- 理屈はわかっていても、今やりたいことに感情が引っ張られてしまう
- 気持ちを自分で切り替えるのはまだ難しく、外からのサポートが必要
- 「習慣」「順番」「決まった合図」があると、気持ちの橋渡しになりやすい
つまり、「やりたくない」ではなく、
「やめ方がわからない」「区切りをつける手段がない」という状態なのです。 - 親にできる工夫
-
- 「あと3回でおしまいね」「タイマーが鳴ったらごはん」など、予告・見通しを伝える
- 「まだ遊びたいんだよね。でも…」と、共感語で気持ちを受け止めたうえで提案
- 行動そのものよりも、“気持ちが切り替えやすい環境”を整えることがポイント
例:
「まだ遊びたいよね。でも時計が7になったらごはんって決めたよね。」
「タイマーが鳴ったよ。お皿並べるの手伝ってくれる?」「やめなさい」より、「区切りを一緒に作る」声かけが、子どもにとっても心の準備になります。
【5〜6歳】“わかってるのにできない”心の葛藤の時期
- 特徴
-
5〜6歳になると、話の内容や理由もだいぶ理解できるようになり、「我慢」や「順番」も意識できる場面が増えてきます。
それなのに、実際には同じことで何度も注意されたり、反発したりする…そんな場面に、モヤモヤした経験はありませんか?
この時期の子どもは「理解はしているけれど、納得していないと動けない」という内的な葛藤を抱えやすくなります。
- よくある困りごと
-
- 「片づけて」と何度言ってもダラダラ…結局やらない
- 注意すると「今やろうとしてたのに!」と怒る、逆ギレする
- 叱ったら無言・泣き出す・部屋を出ていくなど感情で反応
大人から見ると「わかってるのに、なんでやらないの?」と思いがちですが、
子ども自身も「どうしてもうまくいかない」もどかしさを感じていることがあります。
- 背景にある“こころの動き”
-
- 理屈で理解できても、感情の波や疲れに左右されやすい
- 自尊心が芽生え始め、「失敗したくない」「怒られたくない」気持ちが強くなる
- 親の言葉を、行動への指示ではなく“自分への評価”と受け取りやすい時期でもある
「何でできないの?」と言われると、「自分はダメなんだ」と思い込みやすくなるのがこの年齢です。
- 親にできる工夫
-
- 命令や指示よりも、「どうしたらうまくいきそうかな?」と相談スタイルで声をかける
- 小さな“できた”を見つけて、「そこ気づいたね」「昨日より早かったよ」と具体的に認める
- 感情が高ぶっているときは、一度クールダウンできる時間や場所を用意してあげる
例:
「今日は疲れてるよね。じゃあ10分だけ休憩して、それから一緒にやってみようか?」自分の気持ちを理解してもらえたと感じたとき、子どもは安心して行動に移しやすくなります。


親の関わり方で変わる|実践アプローチと声かけ例
子どもが「言うことを聞かない」とき、それを“わざと”と受け取ってしまうと、親もストレスを感じやすくなります。
しかし、実際には発達段階に応じて「まだ聞けない」状態であることが多いのです。
このセクションでは、親が実践できる関わり方と、実際に効果を感じた事例を年齢別にまとめて紹介します。
【共通の基本姿勢】
- 伝え方を工夫する:命令口調ではなく、具体的で届きやすい言い方に
- 感情を受け止める:まず“共感語”から入ることで心が開きやすくなる
- 選ばせる・待つ:行動の主導権を持たせると納得感が増す
- 小さなできたを認める:自己肯定感の土台を育む
年齢別|聞けなかった子が「聞けるようになった」実践例集
| 年齢 | 困りごと | 有効だった親の対応 | 実際の変化・成功事例 |
|---|---|---|---|
| 1〜1.5歳 | 呼びかけに反応しない / 危ないものを触りたがる | 言葉で制止せず、身体をそっと止めて別の物に興味を向ける | 危険行動の回数が減り、親の動きに自然と注目するようになった |
| 1.5〜3歳 | イヤイヤ・癇癪・拒否反応 / ふざける | 「〇〇したいんだね」と共感した上で選択肢を提示 | 癇癪が短くなり、自分から「こっちにする」と言うことが増えた |
| 3〜5歳 | 終わらない・切り替えられない / 「やだ!」で止まる | タイマー・カウントダウン・事前予告を導入、「あと1回でおしまい」と視覚化 | 「ピッてなったらやめる」が定着し、親子ともにストレスが軽減 |
| 5〜6歳 | 理屈は通じるのに反発 / 無視・拗ねる | 「どうしたらやれそう?」と相談形式で聞き、選択権を渡す | 「今は休憩したい」と自分の気持ちを言葉にできるようになった |
声かけ変換例
子どもは、否定的な言葉よりも、
具体的な行動提案や努力の過程を肯定する言葉の方が、受け入れやすく安心しやすい傾向があります。
| NGワード | ポジティブな言い換え |
|---|---|
| なんで言うこと聞けないの? | おもちゃは箱に入れてね |
| 早くして! | あと3分で出発だよ、靴をはこうか |
| ほんとダメね | 惜しかったね、あと少しだったよ |
| またやってる! | 今気づけたね、それってすごいよ |
【伝え方のコツ】
- 声をかける前にテレビや音を止める
- 目を見て、一呼吸おいてから話す
- 「今やること/あとでやること」を明確に分けて伝える
- 急いでいるときほど、行動の“見通し”を共有する工夫(〇〇したら△△)
“届く関わり”が、自己肯定感の芽になる
子どもが「言うことを聞かない」とき、それは大人にとって“試練”のように感じるかもしれません。でも、実際にはその瞬間こそが、親子の関係性を育むチャンスでもあります。
- 無理やり従わせようとしない
- 感情や状況を“理解して寄り添う”姿勢を持つ
- そして、できたときにしっかりと言葉で認める
こうした積み重ねが、子どもの「自分は大丈夫」「ちゃんと聞ける子なんだ」という感覚を育てていきます。
親自身も完璧を目指さず、“うまくいかない日があってもいい”と許せる気持ちを持ちましょう。
そんな関わりこそが、子どもの心を開く力になります。
まとめ
子どもが言うことを聞かないのは、「聞く気がない」のではなく、“まだ聞けない状態”であることが多いのです。
親の関わり方をほんの少し変えるだけで、子どもとのやりとりがスムーズになるきっかけを作ることができます。
- 年齢に合った期待を持つ
- シンプルで具体的な声かけをする
- 待つ・選ばせる・共感する姿勢を意識する
- 「できたこと」に目を向けて声をかける
子どもに“できるようになる日”は、必ずやってきます。
焦らず、比べず、日々のやりとりを丁寧に積み重ねていきましょう。
そしてなにより大切なのは、親自身が「うまくいかない日もあっていい」と思えることです。
親子の関係性をより良いものにするために、「言うことを聞かない」日々もまた、育児をアップデートする貴重なヒントになるはずです。