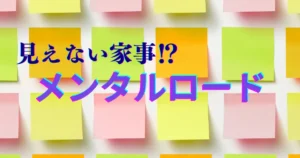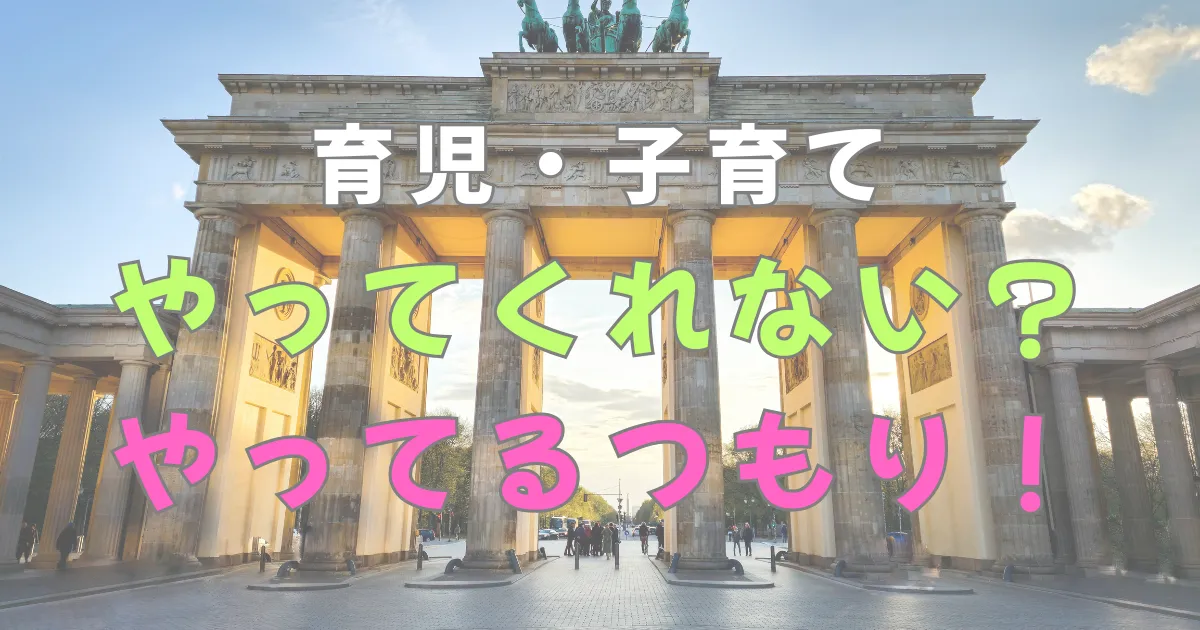「育児や家事は気づいた方がやる」
「得意な方がやればいい」
そう思っていたのに、気づけば家のことはほとんど自分の担当になっている。
「夫にもっと関わってほしい」と思う一方で、伝え方がわからない。
「妻がなんでも決めているように見えて、自分が入る隙がない」と感じることも。
そのすれ違いの背景には、ゲートキーピングという心理的な壁があるのかもしれません。
- ゲートキーピングとは何か?
- なぜ、夫婦の間に見えない壁が生まれるのか?
- ふたりで育児を進めていくためのヒント
\ ゲートキーピングについてもっと詳しくみる /
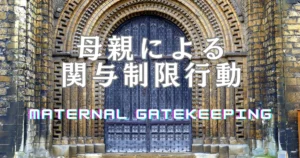

ゲートキーピングとは?

ゲートキーピング(gatekeeping)とは、もともと情報の出入りを管理するという意味を持つ言葉です。
育児においては、“子どもに関わること”へのアクセスを誰がコントロールしているかという心理的な構造を指します。
たとえば──
- 育児の判断をすべて自分で行い、パートナーのやり方に否定的になってしまう
= マターナルゲートキーピング
(主に母親) - 何か言われるくらいなら最初から関与しない、と育児から一歩引いてしまう
= パターナルゲートキーピング
(主に父親)
なぜ、このような心理が生まれるのか?
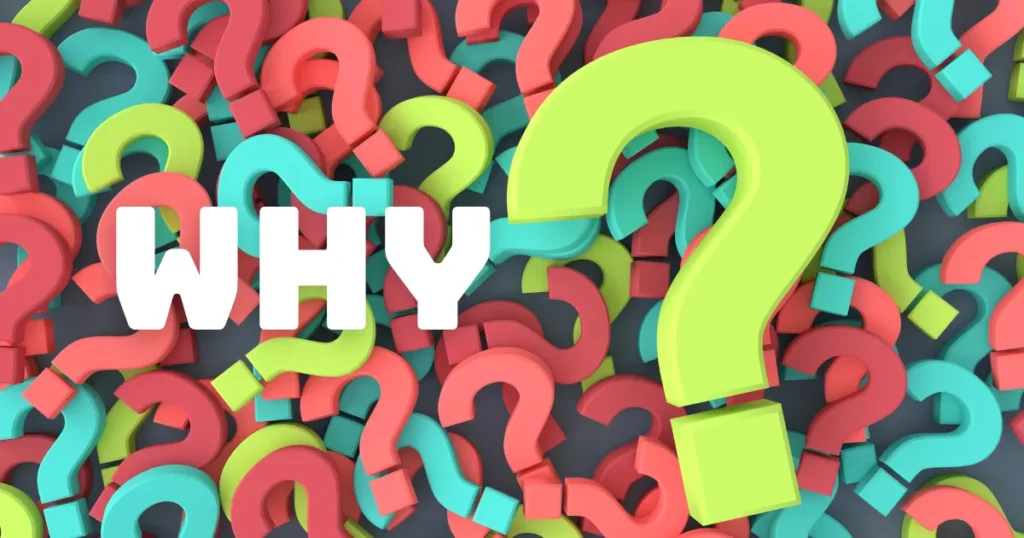
背景にあるのは、積み重ねたすれ違い
育児におけるゲートは、一方的に閉ざされるのではなく、夫婦の関係性の中で徐々に形作られていきます。
- 「ちゃんとやってほしい」から指示が細かくなる
- 「どうせまた注意される」と感じて関わらなくなる
すれ違いが繰り返されることで、気づけば育児の主導権がどちらか一方に偏り、「任せられない」「関わりづらい」といった思いが強まってしまうのです。
背景には、以下のような要因が関係しています。
- 育児に関する情報や経験の偏り
-
育休取得や出産を機に、どうしても片方に育児経験が集中しやすくなります。
すると「自分がやった方が早い」という気持ちや、「やり方が違って気になる」といった感情が強まりやすくなります。
- 性別役割の刷り込み
-
「母親が育児の中心であるべき」
「父親は仕事で稼ぐ方が重要」こうした社会的な価値観が、無意識のうちに役割を固定化させてしまうケースもあります。
- 認識のズレ
-
「任せる=手を抜く」と感じてしまったり、「やっても否定される」という体験から、
「だったら、やらない・やらせない」という選択をしてしまう。こうした“認識のズレ”も、育児の共有を阻む見えない壁になります。
すれ違いが引き起こす影響
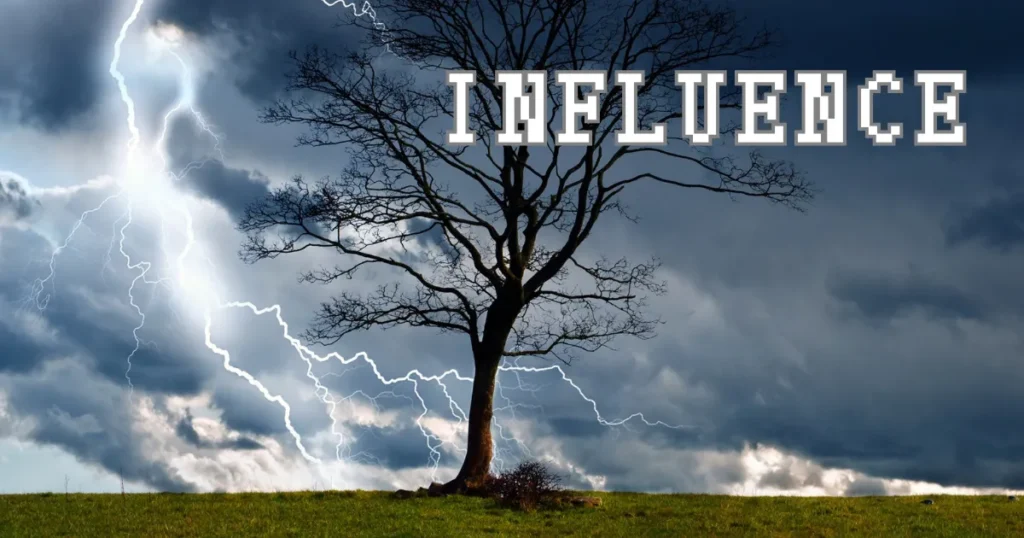
分担ではなく“孤立”に向かっていくリスク
育児におけるゲートキーピングが続くと、次のような影響が生じやすくなります。
- どちらか一方だけが疲弊し、気持ちに余裕がなくなる
- 関与しなかった側が“子どものことがわからない”状態に
- 「わかってもらえない」という感情的な断絶が深まる
- 子どもが一方の親とのみに依存するようになりやすい
ふたりで育児に向き合うためのヒント

それぞれの思いや経験に違いがあるからこそ、どちらかが変わるのではなく、ふたりで調整していくことが大切です。
以下に、具体的なヒントをご紹介します。
①「決めないと動けない」仕組みを見直す
育児に関する決定権や情報が片方に偏っていませんか?
- 保育園の持ち物やルール
- 食事や生活リズムの方針
- 病院やスケジュール管理
このような「判断ポイント」を共有・可視化していくことで、もう一方も関与しやすくなります。
② やり方の違いを尊重する
「自分と違う=間違い」ではなく、「違う=別の関わり方」として受け止める視点が重要です。
- どちらが正しいかではなく、子どもにとってどうかという視点でみる
- 「失敗も含めて育児」と考える余裕を持つ
違ってもいいんです。
むしろ多様な関わりこそが、子どもの安心感や柔軟性を育む要素にもなります。
③ 小さな「共同作業」から始める
いきなりすべてを一緒にやろうとすると、かえって摩擦が生まれます。
- 送迎をどちらかが担当してみる
- お風呂タイムを“父と子の時間”にしてみる
- 寝かしつけや読み聞かせを役割分担する
こうした関わりを少しずつ増やしていくことが、ゲートをゆるやかに開いていく第一歩です。
④ 「ありがとう」と「気づき」を伝える
当たり前のことを「伝え合う」だけでも、信頼の土台が強化されます。
- 「ありがとう、助かったよ」
- 「あの時こうしてくれて嬉しかった」
- 「このやり方もありだね」
相手の行動を評価ではなく、共有として受け取る。
この視点が、パートナーの“関わる勇気”を育てていきます。
まとめ
育児における役割は、一度決めたら変わらないものではなく、家族の状況や子どもの成長に合わせて、柔軟に見直していけるものです。
違和感を感じたときこそが、関係をアップデートするチャンス。
「自分がやらなきゃ」ではなく、「任せていい」「任されていい」という感覚を、ふたりのあいだに育てていくことが大切です。
育児は、ひとりで背負うものではありません。
“チームとして支え合うこと”が、家族のかたちを深めてくれます。
ゲートを少しずつ開いていくことで、家庭の中に、もっと自由であたたかな空気が流れ始めるはずです。
ふたりでつくる育児へ。
今この瞬間、できることから少しずつアップデートしていきましょう。